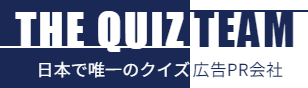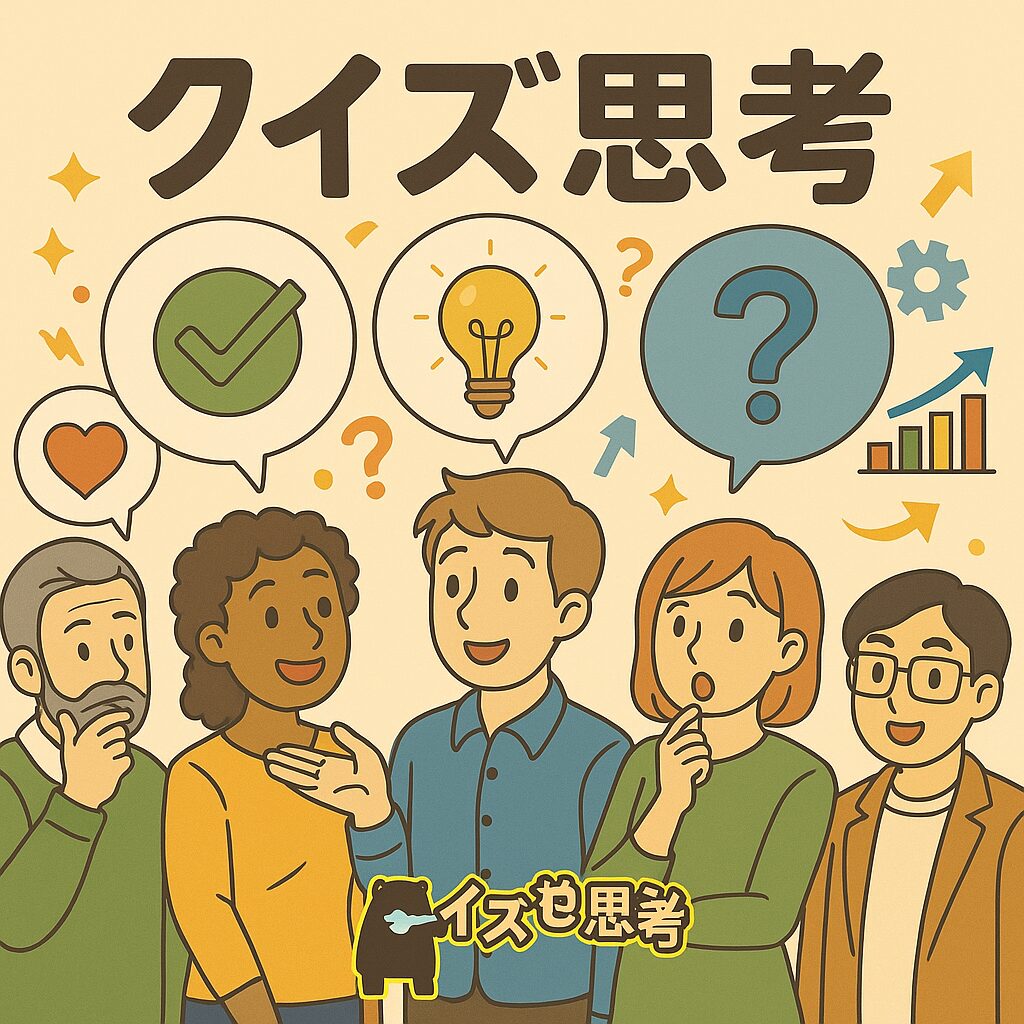― 情報過多の時代を生き抜く、クイズ思考の使い方 ―
Googleを開けば、どんな知識も3秒で出てくる時代。
誰でも“答え”には簡単にアクセスできる。
さらに付随する「余計なこと」もAIが教えてくれる。
でも、それって本当に「わかった」ってことになるのだろうか?
むしろ、「何を検索するか」=どんな問いを立てられるかのほうが重要になってきていないか。
「答え」は誰でも持ってる。でも…
たとえば、「SDGsとは何か?」を調べれば、1秒で答えは出てくる。
でも、「自分の仕事とSDGsって、どう関係あるんだろう?」という問いを立てられる人はどれくらいいるだろう。
「自動運転とは?」よりも
「この技術が高齢化社会にどんな変化を与えるか?」と考える人が、未来を変える。
“問いを作る力”=“考える力”
クイズをつくるには、「何を聞くか?」を徹底的に考える。
これは実は、編集力であり、構造化スキルであり、他者視点でもある。
相手がどこでひっかかるか?
どう答えたくなるか?
どんな順番で情報を出せば気づきが生まれるか?
クイズをつくるプロセス=思考のトレーニングなのだ。
正解より、「問い」のある人が選ばれる
今、あらゆる業界で問われているのは「クリティカルシンキング」や「対話力」。
でもその源は、“問い”を立てる力。
「何を知っているか」より、「何を問えるか」。
この力が、あなたの価値を左右する。
✨クイズ思考を、日常に持ち帰ろう
「これは何のためにあるのか?」
「これって他にも応用できないか?」
「もし逆だったらどうなる?」
そんな風に問いを立てる癖がつけば、
通勤電車も、会議も、広告も、全部が“ネタの宝庫”に見えてくる。
答えは変わっていく。
でも、良い問いは残る。
そして、良い問いは、人を動かす。
これからの時代、「問いを持っている人」が、チームを導き、世界を動かす。
それを信じて、今日もクイズを作っています。
次回予告
「“間違えること”は最高の成長装置」
― クイズと失敗の意外な関係